地域のおける口腔ヘルスケアの展望
Perspectives of Community Oral Health Car
高江洲 義矩
(東京歯科大学名誉教授)
はじめに
「口腔ヘルスケア(oral health care)」という表現は、従来の歯科保健と同じ領域を意味するものであるが、「ケア」が付加されたことでどこか変わった印象を与えている。1970年代前後から世界的に使われてきている用語である。それに対して、「歯科保健(dental health)」は、歯科領域に限定した「保健」という表示であり、あるいは歯科領域に関連するということである。
では、なぜ「口腔保健」とか「口腔ヘルス」と表示するような背景があるのか、そしてなぜ「口腔保健」に「ケア」を付加するのかということに関連して地域保健の課題と展望を考えてみたい。
1. 歯科保健と口腔保健の相違
世の中には流行というものがある。流行語というのもあり、その時代を適切に表現していることがよくある。その中でも医歯系の用語の殆どは学術団体と公的機関で、ある程度まで用語を決めているので、いつの時代にもそれに準じて用語が使われている。
しかし、国際会議や国際機関などで審議されて新しい用語が台頭してくることもある。そのことから、世界的な用語の動向みたいなものが、わが国で慣用的に使われていた用語に影響を与えることもある。
ここに挙げた「歯科保健(dental health)」と「口腔保健(oral health)」、さらに「口腔ヘルスケア(oral health care)」は、1970年代頃から同義語的に使われてきている。その用語に微妙な相違を感じながらも、それぞれ適当に使い分けられてはいる。
「歯科保健」は医科に対しての標榜であるが、どこかに専門的な立場での意向が漂っている。つまり「あなたの歯・口の健康」、「私の歯・口の健康」というよりも、「歯科医療側からの歯・口の健康」であり、それがどのように「全身の健康につながっているか」という課題を示しているように思われる。実際にそのような印象で受けとられていることも事実のようである。そこで、この歯科保健の表現にならって医科の各科を当てはめてみるとどのような印象になるだろうか? たとえば小児科保健、産婦人科保健、耳鼻科保健、眼科保健などと。どうも「科」を入れると、前述のような印象を与えるように思える。
一方、「口腔保健」は、従来は「口腔衛生」であったので、英語に直訳すれば“dental hygiene”になるわけであるが、米国では20世紀初頭から、デンタル・ハイジ-ンとは、歯口清掃(口腔清掃)を意味する慣用語でもあった。それで、わが国でもここ50数年ぐらい“dental health“と英訳されてきた。この「口腔衛生」の日本語表現も、永いこと「こうこうえいせい」と発音され、「口腔衛生週間(こうこうえいせいしゅうかん)」と新聞紙上に書かれていた。学校の先生方も児童生徒さん達を前に「皆さん、今日から”こうこう衛生週間“ですので、よく歯をみがきましょう」ということになっていた。殆どの日刊新聞やNHK放送などでも、つい十年程前まで「こうこうえいせい」と表現することがあった。確かに国語辞典では「こうくう」は「こうこう」の慣用語と記載されているので、正式には「こうこう」と表現することになる。ちなみに広辞苑の第5版(1997)でみると、ようやく「医学ではコウクウという。」と始めて受け入れてくれたようである。「医学では口腔外科(コウクウげか)という。」とある。ただし「医学では」となっている。最近の医道審議会での医科歯科標榜の審議の際にも、口腔外科は医学系であると決めつけられたいきさつがある。ところで同じ辞典の「こうこう」を引くと、相変わらず「口腔衛生(こうこうえいせい)、口腔外科(こうこうげか)」となっている これまでにも、「口腔衛生」の日本語が「航空衛生」と聞き間違えられて、「何か飛行機の関係ですか」と問われて苦笑することが時にはあった。これが、時代は変わって「口腔保健」となると、今度は「航空保険」と聞き間違えられることがあり、これまた定着するまでには時間を要するであろうし、そのことは笑い話しではなく、歯科界の用語が国民的市民権を得ているか否かの問題である。単なる笑い話しでは済まされないことである。
さて、「歯科保健」に対して「口腔保健」はどのような意義を持つのだろうか? 口腔の健康のことであるので、歯科という限定表現はない。この用語を直截的にとれば、「あなたの歯・口」であり、「私の歯・口」である。この時代になって、この種の用語にも主体性が感じられるようになってきたように思う。歯・口に関する人々の意識・認識が変わってきたことも、この用語に反映されていることであろうか。
“oral health careモを日本語でどのように表わそうかと苦心したことがあった。「口腔保健看護?」、「口腔保健介助?」、「口腔保健配慮?」etc.。いずれも翻訳不可能である。「口腔保健ケア」、「口腔ヘルス・ケア」、「口腔ヘルスケア」、「オ-ラル・ヘルス・ケア」、「オ-ラル・ヘルスケア」など、どうにもおさまらないことである。実際に「ケア」という用語そのものは翻訳なしで日本語化してきている。私は「口腔ヘルスケア」を用いるように心がけている。“health care“は、現在では欧米でも”healthcare“と一語綴りになってきている。
「口腔ヘルスケア」を意味する内容で、わが国でよく用いられている用語がある。「口腔ケア」という用語である。ただし、英訳して“oral care”と表現しても一般的な表現ではないようだ。つまり、“oral care”とすると、英語的表現では「口でケアする」ということかと、とっさには感違いするようである。しかし、最近のイギリスでの用語で“holistic oral care”という用語が使われている。つまり、holisticという形容詞がつくと、次ぎのoral careが理解できるということである。 現在、わが国では「口腔ケア」が一般的な用語として、保健医療の行政や医療関連領域でよく使われている。したがって、行政レベルでの地域歯科保健活動も意味し、さらに個人的なケアのレベルでの用語でもある。
2.サ-ビスとケア
用語の厳密な定義ではないが、医療行政・保健行政・福祉行政でよく使われている用語に「サ-ビス」と「ケア」がある。
「サ-ビス」が主として専門家側・職業人側から患者または住民・消費者へのある種のアクション(行動・行為)であるのに対して、「ケア」は相手の身になって、目線を同じくして、共有する場での対応・アクション(行動・行為)であり、配慮であるということで使われている。
WHOは、長い間、公衆衛生サ-ビスpublic health serviceの用語を用いてきていたが、1970年前後から公衆衛生ケアpublic health careまたは地域保健ケアcommunity health careの用語を盛んに使うようになってきた。ただし、health care serviceという「ケアとサ-ビスを合わせた保健行政用語」もある。さらに今では“healthcare” が一綴りの一語にもなっている。
“ケア”という用語は、看護領域での用語であり、“care”、“caring”としての一般的な表現である。ところが、“コミュニティ・ケア”となると、この用語の本来の意味は、精神障害者の開放型病院などのように、1899年の南フランスのToulouseにおける解放病棟の歴史にまで遡ることになる。つまり地域におけるケアとしてのコミュニティ・ケアであり、さらに北欧を中心とした福祉事業におけるコミュニティ・ケアに端を発することになる。障害者を地域でいかにケアするかという社会的な運動としてのケアである。今日では、保健と医療と福祉が合体していく時代(保健医療福祉複合体)であるので、「ケア」は共用語となってきている。
3.医療の求心性と遠心性
医療と福祉には、その発達の時点から制度上の境界が発生してきたようである。本来、人間を中心に、患者を中心に考えれば両者に境界があるわけではない。その弊害は、20世紀末になってようやく取り除かれてきたようである。しかし、それだけにいくつかの混乱を抱えたまま今世紀に入っている。
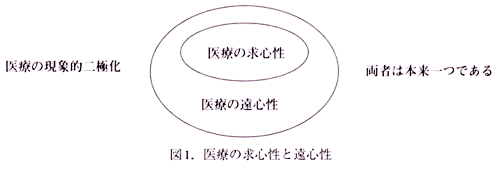
医療を患者側からではなく、医療人側からみると、患者や悩める人達のために絶えず技術革新と技術開発で進められている。それは“よりよい医療”への技術的改善であり、“患者側の要望に沿うような医療”への展開でもある。そして、そのこと自体が医療の本質的な内在的エネルギ-でもある。たとえば、「臓器移植」、「ゲノム医療」、「再生医 療」など。歯科では「インプラント」など。これを「医療の求心性」と呼んでおく。
しかしながら、その内在的な技術探求が、時に「医の倫理」で揺さぶられることがある。かなり倫理的なリスクを伴うエントロピ-である。
その一方で、医療は本質的に人類の福祉を担うものであるので、治療で人々を救うだけでなく、予防を優先して進められてきている。それが「医療の本質」であり、さらに医療技術だけでは癒すことのできない人間性の生き方を支援する「癒しの医療」あるいは「ケアの本質」に基づく医療と福祉が進められている。この領域を「医療の遠心性」と表現しておく。
このように、本来、患者のために一つであるべき医療に「二極化した現象」がみられ、 そのことが「医療の空洞化現象」を発生させて医療倫理や医療事故の問題となることがある。
それは言うまでもなく、医療制度と社会保障制度の在り方に大きく影響されていることである。20世紀までの医療は、急激な技術革新による医療のために、医療そのものと福祉との連携に混乱を抱えた時代であった。 これからの医療は、予防に重点をおくことは当然であるが、それだけでは解決しないであろう。むしろ医療技術の根本的な「技術倫理」が「生命科学の理念」に根ざしたものでなければならないところの瀬戸際に遭遇している。科学的であるだけではなく、「生命科学」という新しい理念の科学が切実に求められている。
4.地域保健のコア概念と連携モデルのトポロジ-(位相性)
“地域保健”と“公衆衛生”が同義語的に用いられてきたが、公衆衛生には“衛生思想の普及”という用語がつきまとって印象づけられてきた。英語では“sanitary(衛生) とか”hygiene(衛生)“という言葉が永く使われていたように、国策としての伝染病対策に主眼をおいてきた経緯がある。
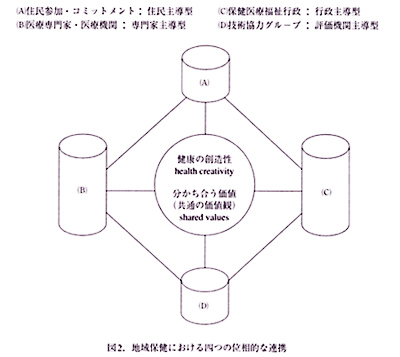
ところが、現在では“community health”の地域保健が主流になってきている。「公衆衛生」が環境科学と生命科学による検証で進められている現状に対して、「地域保健」は個人の人権(human rights)から地域全体の保健政策を対象としてきていることにその特徴が表われている。しかも、その場合の主体が地域、つまり地方自治体に重点が置かれていることで、1994年に「地域保健法」そのものの誕生となっている。
図2.に示されるように、地域やコミュニティで進められる健康づくり運動・保健活動は、理想的に言えば、すべての住民が参加(コミットメント)し、保健医療要員が熱心に従事し、保健医療福祉行政が保健政策に基づいた予算と活動方針を示し、そして何よりもだいじな評価機関によって評価されて、継続的な活動となる。 しかし、現実にはこれらの連携には時代的な較差があり、一般的には医療保健専門家側が主導し、保健医療福祉行政側が漸く予算を出すようになり、それによって住民側が参加するようになってきた歴史的な経緯がみられる。
わが国の地域歯科保健(地域口腔保健)では、とくに定着した評価機関とういのがないのが残念である。目下のところは、歯科医師会や大学歯学部の公衆衛生担当のスタッフが対応している現状である。医科でも医療評価機構はあるが、地域保健の評価機関はみられない。おおかたの県にある予防協会や健康診査センタ-が個人的な健康情報をフィ-ドバックしている。
したがって、このモデルの中で、現在でも最も遅れている部門は評価機関であり、それはできるだけ素早く住民側に個別的にデ-タを還元することである。このような較差が生じてしまうことがトポロジカル(位相学的)であり、時代の流れの中での力動的な特性を示している。
むすびとして
新しい時代における「地域口腔ヘルスケア(地域口腔保健、地域歯科保健)」に関連する課題について概略的な展望とした。今回は、口腔保健の現象的な面をとらえて寸評 を試みた。次ぎに機会をみて、その実体と分析からの政策試案およびその解説にとりかかってみることにしたい。
最近の動向としては、保健と医療と福祉の複合体の様相を呈しているが、どうも未整備のまま国民医療費と国民介護費が同時に高騰していくようである。今後、わが国の医療と介護は保険方式でいくのか、それとも租税方式をとりいれるかという大きな課題が待ち構えている。さらに、わが国では保健(health)と医療(medical care)を区別しようとする傾向があるが、欧米では保健と医療は同じく“health”に包括している。そして何よりも保健政策(health policy)を重視している。
しかしながら、わが国の現状をみていると、いつの時代にも現実への対応と対策(countermeasure)のみに追われている。それは当然であるとしても、それにだけに拘泥する姿勢から新しい展開は生まれてこない。世界の歴史をみると、絶えず先見性(foresight)を重視し、しかも現状を分析した洞察力(insight)から新しい時代が拓けている。
文 献
1.Takaesu,Y. : Oral health care program in Community, In Predictable Advances in Oral Health Research, Ed. by Kanatake,T. & Takazoe, I., Tokyo Dental College, 1991.
2. 高江洲義矩:地域歯科保健の理念と現状、公衆衛生,57(8) : 524-529,1993.
3 高江洲義矩:地域のなかの歯科医師の役割と機能、石川達也・高江洲義矩・中村譲治・ 深井穫博 編集「かかりつけ歯科医のための新しいコミュニケ-ション技法.」pp.7-29, 医歯薬出版,東京、2000.
4. 瀧口 徹: 厚生行政の立場から21世紀の歯科保健を考える、公衆衛生、65(7),2001.
5. Mann, J.M., Gruskin, S., Grosin, M.A. and Annas, G.J.(Ed.) : Health and human rights, Routledge, New York and London, 1999.
6 . Pine, C.M.(Ed.) : Community Oral Health, Wright, Oxford, 1997.
7. Gluck, G.M. and Morganstein, W.M. : Jogユs Community Dental Health, 4th ed. Mosby, St.Louis, 1998.


